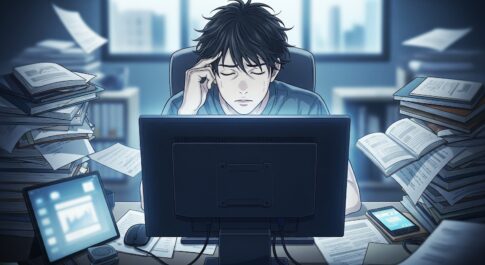「過度な不安や緊張で、仕事がうまくいかない…」
「今の職場は自分に合っていないかもしれないけど、辞めるのも怖い」
「周りからは『気にしすぎ』と言われるけれど、自分ではコントロールできなくて辛い」
この記事は、そんな不安症(不安障がい)の症状と向き合いながら、自分らしく働くための道筋を書きました。症状によって生じる困難は、決してあなたの能力や意欲の問題ではありません。正しい知識を身につけ、適切な工夫やサポートを活用することで、安心してキャリアを築いていくことは十分に可能です。
この記事を最後まで読むことで、以下の点が明確になります。
- 不安症の基本的な知識と、仕事のパフォーマンスや心身に与える具体的な影響
- 電話応対や会議など、多くの人が直面する「仕事上の困りごと」とその背景
- 仕事を続けるために今日からできるセルフケアと、職場で活用できる「合理的配慮」の具体例
- ご自身の特性に合った、続けやすい仕事・避けたほうがいい仕事の判断基準
- 一人で抱え込まずに頼れる「就労移行支援」や公的なサポート制度の詳細
この記事は、不安と向き合いながら、自分に合った働き方を見つけたいと願う、以下のような方々に向けて執筆しています。
- 強い不安や緊張で仕事でのミスが増えたり、人間関係に悩んだりしている方
- 今の仕事が心身の負担になっており、転職を考えているが次の一歩が踏み出せない方
- 自分の症状に理解のある職場で、無理なく安定して働き続けたいと願う方
- 利用できる制度やサポートについて知り、専門家の助けを借りながら自分らしいキャリアプランを考えたい方
この記事が、あなたの抱える不安を少しでも和らげ、自分らしい働き方を見つけるための、信頼できる道しるべとなれば幸いです。
Contents
不安症(不安障がい)とは何か

不安症の定義と症状
不安症(不安障がい)とは、日常で感じるような一時的な不安とは異なり、過剰で持続的な不安や恐怖によって、日常生活や社会生活に大きな支障が生じている状態を指します。不安という感情そのものは、危険を察知し、それに備えるための自然な反応です。しかし、その反応が過剰に、そしてコントロールできないほど強くなると、心身にさまざまな不調が現れます。
不安症の症状は、精神的なものと身体的なものに大別されます。
■精神的な症状
- 特定の対象がないにもかかわらず、常に何かを心配してしまう
- 緊張感が抜けず、リラックスできない
- 物事に集中できない
- ささいなことでイライラしてしまう
- 危険が迫っているような強い恐怖感に襲われる
■身体的な症状
- 動悸、息切れ、胸の圧迫感
- めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ
- 手足の震えやしびれ
- 過度な発汗
- 吐き気、腹痛、下痢
- 頭痛、肩こり
- 不眠、または寝ても疲れがとれない
また、不安症は一つの病気ではなく、症状の現れ方によっていくつかの種類に分類されます。代表的なものには以下のような種類があります。
| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| パニック症(パニック障がい) | 突然、理由もなく激しい動悸や息苦しさ、めまいなどの発作(パニック発作)が起こり、「また発作が起きたらどうしよう」という強い予期不安を感じます。 |
| 社交不安症(社交不安障がい) | 人前で話す、注目を浴びる、人と食事をするなどの社会的状況に対して、強い恐怖や不安を感じ、そうした場面を避けようとします。 |
| 全般不安症(全般不安障がい) | 仕事、健康、家族のことなど、生活上のさまざまな出来事に対して、コントロールできない過剰な心配や不安が長期間(6ヶ月以上)続きます。 |
| 特定の恐怖症 | 高い場所、狭い場所、特定の動物や昆虫、注射など、特定の対象や状況に対して、極端な恐怖を感じます。 |
これらの症状は、本人の意思の弱さや性格の問題ではなく、治療によって改善が期待できるものです。気になる症状がある場合は、専門の医療機関に相談することが大切です。
不安症の原因と影響
不安症がなぜ起こるのか、その原因は一つに特定できるものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。主な原因として、以下の3つが挙げられます。
- 脳機能の要因 不安や恐怖といった感情をコントロールする脳の部位の機能的な問題や、セロトニン、ノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスの乱れが関係していると指摘されています。これらは、生まれ持った体質的な要素も影響します。
- 心理的な要因 物事を悲観的に捉えやすい、完璧を求めすぎる、自己評価が低いといった認知の特性や性格傾向が、不安を感じやすくさせる一因となることがあります。過去のつらい経験がトラウマとなり、特定の状況に対して過敏に反応してしまうケースもあります。
- 環境的な要因 仕事上の強いプレッシャー、人間関係のトラブル、身近な人との別れ、経済的な問題など、強いストレスとなる出来事が発症の引き金となる場合があります。また、幼少期の家庭環境なども、その人のストレスへの対処能力に影響を与えることがあります。
これらの原因によって生じる不安症は、個人の生活にさまざまな影響を及ぼします。日常生活においては、外出を避けたり、人との交流を断ったりすることで社会的に孤立しがちになります。また、常に緊張状態が続くため、十分な休息がとれず、慢性的な疲労感や不眠につながることも少なくありません。
仕事や学業の面では、集中力の低下や判断力の鈍りから、パフォーマンスに影響が出ることがあります。特に、電話応対やプレゼンテーション、会議での発言といった特定の状況に強い苦痛を感じ、キャリア形成や学業継続の妨げとなるケースも見られます。
さらに、不安から特定の行動を避けることが、かえって不安を強めてしまうという悪循環に陥ることもあります。例えば、人前で話すのが怖くて避けていると、成功体験を積む機会を失い、ますます苦手意識と不安が募ってしまうのです。このように、不安症は心身の健康だけでなく、社会的な活動全般に影響を及ぼす可能性があります。
不安症(不安障がい)の方が直面する仕事上の困りごと
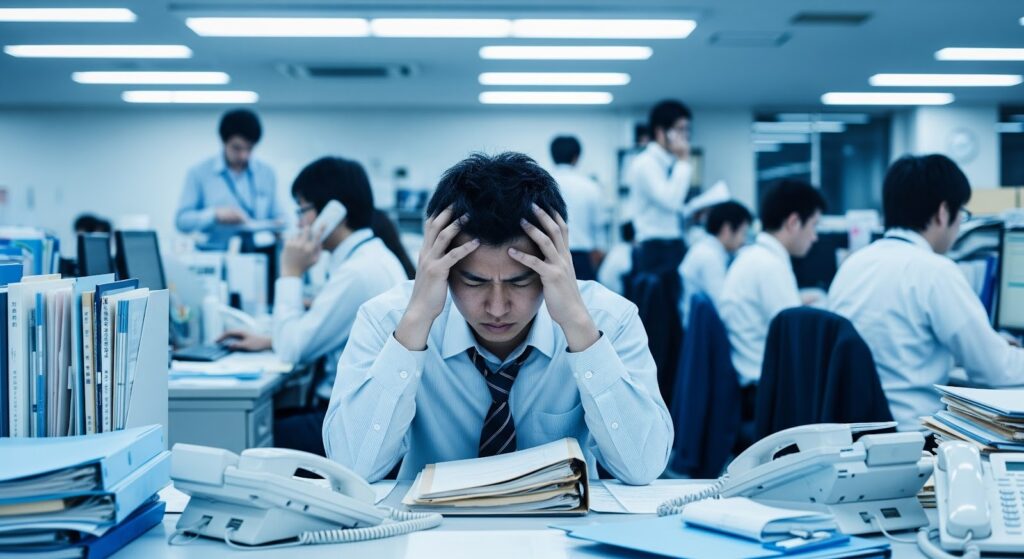
仕事における具体的な困難
不安症の症状は、仕事のさまざまな場面で困難を引き起こす可能性があります。本人の能力や意欲とは関係なく、症状によって業務の遂行や職場でのコミュニケーションに支障が出てしまうことは少なくありません。具体的には、以下のような困りごとが挙げられます。
- コミュニケーションへの支障 電話応対や会議での発言、上司への報告、同僚との雑談など、人とのやりとりに強い緊張や不安を感じ、避けてしまうことがあります。その結果、必要な情報共有が滞ったり、周囲から孤立してしまったりするケースがあります。
- 業務パフォーマンスの低下 常に何かしらの心配事にとらわれているため、目の前の業務に集中することが難しくなります。ミスを過度に恐れるあまり、何度も確認作業を繰り返して時間がかかったり、重要な決断を先延ばしにしたりすることもあります。
- 特定の状況や環境への困難 パニック発作の経験がある方は、通勤電車やエレベーター、閉鎖的な会議室といった特定の場所に対して強い恐怖を感じ、出社自体が困難になる場合があります。また、人混みや騒がしいオフィス環境が、不安感を増大させる要因となることもあります。
- 心身の不調と勤怠の乱れ 持続的な緊張や不眠により、慢性的な疲労感や体調不良を抱えやすくなります。突然の動悸やめまいといった身体症状で業務を中断せざるを得なくなったり、欠勤や遅刻が増えたりすることもあります。
- 周囲からの誤解 不安からくる行動が、周囲からは「やる気がない」「協調性がない」「気にしすぎ」などと誤解されてしまうことがあります。症状への理解が得られないことで、さらに職場での居心地の悪さを感じ、孤立感を深めてしまうことも少なくありません。
社会不安障害の症状と影響
不安症のなかでも、特に仕事への影響が大きいとされるのが社交不安症(社会不安障害)です。これは、他者から注目される状況や、人前で恥ずかしい思いをするかもしれないという状況に対して、著しい恐怖や不安を感じる状態を指します。
仕事においては、以下のような場面で特に強い苦痛を感じる傾向があります。
- 会議や朝礼での発言、プレゼンテーション 大勢の視線が自分に集中することで、「うまく話せないのではないか」「変に思われるのではないか」という不安が極度に高まります。声が震える、顔が赤くなる、汗をかくといった身体的な反応が現れることもあり、それがさらに不安を増大させる悪循環に陥りがちです。
- 電話応対や来客対応 相手の反応を気にしすぎるあまり、言葉に詰まったり、要点をうまく伝えられなかったりします。特に電話では相手の表情が見えないため、ネガティブな反応を想像してしまい、恐怖心を感じることがあります。
- 上司や先輩への報告・連絡・相談 自分の言動が評価されるという意識から、「否定されたらどうしよう」「能力が低いと思われたくない」という不安が強くなり、必要なコミュニケーションをためらってしまうことがあります。
- 職場の雑談や昼食、懇親会 何を話せばいいか分からず、沈黙が怖くなるなど、業務外の気軽なコミュニケーションも大きなストレスとなります。輪に入れないことで孤立感を覚えたり、参加を避けることで「付き合いが悪い」と誤解されたりすることもあります。
こうした状況を避ける「回避行動」が続くと、重要な業務を任せてもらえなくなったり、昇進の機会を逃したりするなど、キャリア形成に大きな影響が及ぶ可能性があります。また、毎日の出勤が強いストレスとなり、休職や離職につながるケースも少なくありません。
不安症(不安障がい)の方が仕事を続けるための工夫

日常生活の改善ポイント
不安症の症状と付き合いながら仕事を続けるためには、まず心身の土台を安定させることが重要です。仕事でのパフォーマンスは、日々の生活習慣に大きく影響されます。調子の波を小さくし、安定した状態で働くためのセルフケアのポイントをいくつかご紹介します。
- 生活リズムを整える 毎日同じ時間に起床・就寝することを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。質の良い睡眠は、不安感を和らげるのに役立ちます。また、栄養バランスの取れた食事を三食決まった時間にとることも、心身の安定につながります。
- 適度な運動を取り入れる ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い運動は、ストレス解消や気分転換に効果的です。運動をすることで、不安に関わる脳内の神経伝達物質のバランスが整えられるとも言われています。無理のない範囲で、継続できるものを見つけることが大切です。
- リラックスできる時間を持つ 仕事の緊張から心と体を解放する時間を意識的に作りましょう。趣味に没頭する、好きな音楽を聴く、ゆっくり入浴するなど、自分が心からリラックスできる方法を見つけて実践することが、ストレスの蓄積を防ぎます。深呼吸や瞑想なども、不安が高まったときに気持ちを落ち着かせるのに有効です。
- 自分の状態を客観的に把握する どのような状況で不安が強くなるのか、体調にどんな変化が現れるのかを日記などに記録してみるのも一つの方法です。自分の状態を客観的に把握することで、事前に対策を立てたり、周囲に説明しやすくなったりします。
- 専門家への相談を続ける 主治医やカウンセラーなど、専門家との定期的な面談は、自分の状態を客観的に見つめ直し、適切なアドバイスをもらうための大切な機会です。一人で抱え込まず、専門家のサポートを継続的に活用しましょう。
職場での合理的配慮の活用
自分自身の工夫に加えて、職場の環境を調整してもらうことも、安定して働き続けるためには非常に有効な手段です。これは「合理的配慮」と呼ばれ、障がいのある人が働きやすくなるように、企業側が個々の状況に応じて行う配慮のことを指します。不安症も、その症状によって業務に支障が出ている場合は、配慮の対象となり得ます。
まずは、自分の症状や苦手なこと、そしてどのような配慮があれば業務を遂行しやすくなるのかを整理してみましょう。その上で、上司や人事部の担当者など、信頼できる相手に相談することが第一歩です。
具体的な配慮の例としては、以下のようなものが考えられます。
| 配慮の種類 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 業務内容の調整 | ・電話応対の業務を免除、または回数を減らしてもらう・会議での発表や司会など、人前に立つ役割を他の人に代わってもらう ・一度に多くの業務を任せず、優先順位を明確に指示してもらう |
| 環境の調整 | ・人通りが少なく、静かで集中しやすい座席に変更してもらう・通勤時の混雑を避けるための時差出勤を許可してもらう ・在宅勤務(テレワーク)を認めてもらう |
| コミュニケーション方法の調整 | ・口頭での指示と合わせて、メールやチャットなど文章でも伝えてもらう・報告や相談を、対面だけでなくチャットツールで行うことを許可してもらう ・会議の議題を事前に共有してもらい、発言内容を準備する時間をもらう |
| 休憩・休暇の取り方 | ・不安が強くなった時に、一時的に休憩できる場所(空き部屋など)を確保してもらう ・通院のための休暇取得に理解を得る |
これらの配慮は、あくまで一例です。大切なのは、自分の症状や業務内容に合わせて、会社側と話し合いながら、お互いにとって無理のない方法を見つけていくことです。一方的に要求するのではなく、「このような配慮をいただければ、この業務で貢献できます」というように、前向きな姿勢で相談することが、円滑な合意形成につながります。
不安症(不安障がい)の方が続けやすい仕事と避けたほうがいい仕事
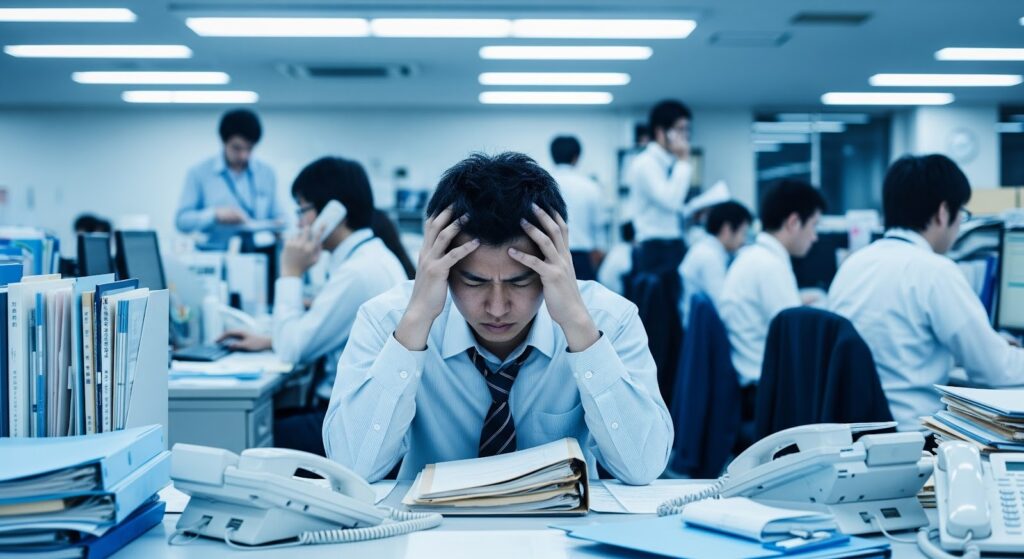
向いている職業の特徴
不安症の症状と付き合いながら無理なく仕事を続けるためには、ご自身の特性を理解し、症状を誘発しにくい環境や業務内容を選ぶことが一つの鍵となります。もちろん、これはあくまで一般的な傾向であり、個人の症状の程度や興味・関心によって最適な仕事は異なります。その上で、不安症の方が比較的働きやすいと感じられる職業の主な特徴を以下に挙げます。
- 自分のペースで進められる 納期やノルマのプレッシャーが少なく、自分の裁量で仕事の進め方やペースを調整できる業務は、焦りや不安を感じにくい傾向があります。突発的な対応が少なく、見通しを立てやすい仕事も含まれます。
- 業務内容が明確で定型的(ルーティンワーク) 作業手順がマニュアル化されていたり、日々行う業務がある程度決まっていたりする仕事は、「次に何をすべきか」「これで合っているだろうか」といった不安が生じにくいです。予測不能な事態への対応が少ないため、精神的な負担を軽減できます。
- 一人で集中できる環境 周囲の視線や雑音が気になりにくく、自分の作業に黙々と取り組める環境は、集中力を維持しやすいです。不特定多数の人と頻繁にやりとりする必要がないため、対人関係のストレスも少なくなります。
- 在宅勤務やリモートワークが可能 通勤時の満員電車や、オフィスという閉鎖された空間が苦手な方にとって、在宅勤務は大きな安心材料となります。自宅という慣れた環境で、自分のペースで働けることは、心身の安定につながります。
- コミュニケーション方法が限定的 電話応対や対面での接客、会議での発表といった場面が少なく、主にメールやチャットなど、文章でのコミュニケーションが中心となる仕事は、社交不安の症状がある方にとって負担が少ないと考えられます。
これらの特徴を持つ具体的な職種の例としては、データ入力、Webライター、プログラマー、経理・事務、清掃、工場での軽作業、文字起こし、校正・校閲などが挙げられます。ただし、同じ職種であっても、会社や部署の環境によって働きやすさは大きく異なるため、応募の際には業務内容や職場環境をよく確認することが重要です。
避けるべき職業の特徴
一方で、ご自身の症状や特性によっては、精神的な負担が大きくなりやすい職業もあります。「向いている職業」と同様に、これもあくまで一般的な傾向ですが、仕事選びの際に慎重に検討したほうがよい職業の特徴を以下に挙げます。
- 高いノルマや時間的なプレッシャーが常にかかる 常に成果を求められ、厳しい納期やノルマに追われる環境は、「達成できなかったらどうしよう」という不安を常に煽る可能性があります。ミスが許されない、あるいは一つのミスが大きな影響を及ぼすような仕事も、過度な緊張につながりやすいでしょう。
- 不特定多数の人との頻繁なコミュニケーションが必須 営業職や接客・販売職、コールセンターのオペレーターなど、初対面の人や多くの人と接する機会が多い仕事は、社交不安の症状を持つ方にとっては大きなストレス源となることがあります。特に、クレーム対応のように、相手のネガティブな感情を受け止めなければならない業務は、心身への負担が大きくなる傾向があります。
- 予測不能な事態への対応が頻繁に求められる トラブル対応や緊急対応など、マニュアル通りに進まない状況に臨機応変に対応する必要がある仕事は、常に緊張を強いられます。「何か起こるかもしれない」という予期不安が強い方にとっては、心休まる時が少なく、疲弊しやすい環境と言えます。
- マルチタスクや迅速な判断力が必要とされる 同時に複数の業務をこなしたり、その場で素早い判断を下したりすることが求められる仕事は、不安によって集中力が低下しがちな状態では、混乱や焦りを招きやすいです。一つひとつの業務に丁寧に取り組みたい方にとっては、ペースについていくのが困難に感じられるかもしれません。
- 競争が激しく、常に他者からの評価にさらされる 成果主義が徹底されており、同僚との競争が激しい環境は、他者からの評価を過度に気にしてしまう傾向がある方にとっては、大きなプレッシャーとなります。会議での発表やプレゼンテーションの機会が多い仕事も、同様に負担を感じやすいでしょう。
これらの特徴を持つ具体的な職種の例としては、営業職、接客・販売職、コールセンター、企業の管理職、イベントプランナーなどが考えられます。
ただし、最も大切なのは、職種名だけで判断するのではなく、その仕事の具体的な業務内容や求められるスキル、職場の環境などを詳しく調べ、ご自身の特性と照らし合わせることです。同じ職種でも、会社の方針やチームの雰囲気によって働きやすさは大きく変わるため、多角的な視点から検討することが重要になります。
不安症(不安障がい)の方が利用できる支援制度

就労移行支援の活用
不安症を抱えながら一人で就職活動を進めたり、働き続けたりすることに難しさを感じる場合、専門的なサポートを受けることが有効な選択肢となります。その一つが「就労移行支援」です。
就労移行支援とは、障がいのある方が一般企業への就職を目指すために利用できる、通所型の福祉サービスです。事業所に通いながら、専門スタッフの支援のもと、就職に必要な知識やスキルの習得、就職活動のサポート、そして就職後の職場定着支援まで、一貫したサポートを受けることができます。
■就労移行支援事業所で受けられる主なサポート内容
- 自己分析とキャリアプランニング 専門の支援員との面談を通して、ご自身の症状の特性や、得意・苦手なことを整理します。それを踏まえ、どのような仕事や職場環境が合っているのかを一緒に考え、無理のないキャリアプランを作成していきます。
- 職業訓練プログラム 個々の目標に合わせて、さまざまなスキルを身につけるためのプログラムが用意されています。
- PCスキル(Word、Excelなど)
- ビジネスマナー、コミュニケーションスキル
- ストレスコントロール、アンガーマネジメントといったセルフケアの方法
- 軽作業などの実践的なトレーニング
- 就職活動のサポート 実際の就職活動を具体的にサポートします。
- 求人情報の探し方、企業研究
- 履歴書や職務経歴書の添削
- 模擬面接(不安な場面への対策)
- 企業見学や職場実習(インターンシップ)への同行
- 就職後の定着支援 就職はゴールではなく、スタートです。働き始めた後も、定期的な面談などを通じて、仕事上の悩みや人間関係の相談に応じてもらえます。また、本人に代わって職場の上司に必要な配慮を伝えてもらうなど、長く安定して働き続けるための環境調整もサポートしてくれます。
不安症の方が就労移行支援を利用するメリットは、障がいへの深い理解がある環境で、自分のペースで準備を進められる点にあります。体調が不安定な時期は通所日数を調整したり、対人関係のトレーニングを少しずつ始めたりと、個々の状況に合わせた柔軟な支援が期待できます。一人で抱え込まずに、専門家と二人三脚で自分に合った働き方を見つけるための、心強いパートナーとなり得ます。利用を検討する場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、各地の就労移行支援事業所に問い合わせてみてください。
公的な支援制度の紹介
就労移行支援のほかにも、不安症の方が安心して治療を続けながら、仕事探しや就労継続を目指すために利用できる公的な制度があります。これらの制度は、経済的な負担の軽減や、個々の状況に合わせた就職活動のサポートを目的としています。
- 精神障害者保健福祉手帳 これは、一定程度の精神障がいの状態にあることを証明するための手帳です。手帳を取得することで、様々な福祉サービスや支援を受けやすくなります。必ずしも取得が必要なわけではありませんが、働き方を考える上での選択肢が広がります。
- 主なメリット
- 税金の控除・減免(所得税、住民税、自動車税など)
- 公共料金などの割引(交通機関、携帯電話料金、公共施設など)
- 障害者雇用枠への応募が可能になる
- 相談・申請窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- 主なメリット
- 自立支援医療(精神通院医療) 不安症を含む精神疾患の治療のため、継続的に通院が必要な方の医療費の自己負担を軽減する制度です。通常3割負担の医療費が原則1割負担となり、所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されます。経済的な心配を減らし、安心して治療を続けるための大きな支えとなります。
- 対象となる医療:診察、薬代、精神科デイケア、訪問看護など
- 相談・申請窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- ハローワーク(公共職業安定所) 全国のハローワークには、障がいのある方の就職を専門にサポートする「専門援助部門」という窓口が設置されています。専門の職員や相談員が、個々の症状や希望を聞き取りながら、職業相談や求人紹介、面接対策など、きめ細やかな支援を提供しています。
- 相談・申請窓口:各地域のハローワーク
- 地域障害者職業センター ハローワークと連携し、より専門的で個別性の高い支援を提供する機関です。一人ひとりの職業的な課題を評価し、必要なスキルを身につけるための職業準備支援や、就職後に職場にスタッフが訪問して本人と企業をサポートする「ジョブコーチ支援」などを実施しています。
- 相談・申請窓口:各都道府県に設置されている地域障害者職業センター
これらの制度をまとめたものが以下の表です。
| 制度名 | 概要 | 主な相談・申請窓口 |
|---|---|---|
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障がいがあることを証明し、様々な福祉サービスや税制上の優遇措置を受けるための手帳。 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
| 自立支援医療(精神通院) | 精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度。 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
| ハローワーク(専門援助部門) | 障がいのある方向けの専門窓口で、職業相談や求人紹介を行う。 | 各地のハローワーク |
| 地域障害者職業センター | 専門的な職業リハビリテーションサービスを提供する機関。 | 各都道府県の障害者職業センター |
どの制度を利用すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけの医療機関の医師やソーシャルワーカー、あるいはお住まいの自治体の障害福祉担当窓口に相談してみるのがよいでしょう。一人で抱え込まず、利用できるサポートを活用することが大切です。
不安症(不安障がい)と向き合いながら働くために

周囲の理解を得る方法
不安症の症状は、外見からは分かりにくいため、そのつらさが周囲に伝わりにくく、「気にしすぎ」「やる気がない」といった誤解を受けてしまうことがあります。安定して仕事を続けていくためには、職場、特に業務上関わりの深い人からの適切な理解と協力を得ることが、大きな助けとなります。しかし、誰に、どこまで、どのように伝えるかは、慎重に考える必要があります。
まず大切なのは、必ずしも職場の全員に打ち明ける必要はないということです。まずは、業務の指示や管理を行う直属の上司や、人事・労務の担当者、産業医など、相談すべき適切な相手を見極めることから始めましょう。その上で、理解を得るための伝え方のポイントをいくつかご紹介します。
- 自分の状態を客観的・具体的に伝える ただ「不安でつらい」と感情的に訴えるだけでは、相手もどう対応してよいか分からず、困惑させてしまう可能性があります。「どのような状況で(例:電話応対、朝礼での発言など)」
「どのような症状が出て(例:動悸、過呼吸、強い緊張など)」
「業務にどのような支障が出ているのか(例:集中できない、報告が遅れるなど)」
を、できるだけ具体的に、事実として伝えることが重要です。事前にメモなどにまとめておくと、落ち着いて話しやすくなります。
- 必要な配慮と、自分にできることをセットで伝える 一方的に配慮を要求するのではなく、
「〇〇という業務は難しいのですが、△△という配慮をいただければ、こちらの□□という業務で貢献できます」というように、前向きな姿勢で相談することが大切です。できないことだけでなく、自分ができることや貢献したいという意欲も合わせて伝えることで、相手は協力的な姿勢になりやすくなります。これは、前の章で触れた「合理的配慮」を求める際の基本となります。
- 医師の診断書や意見書を活用する 口頭での説明だけでは、症状の程度や必要な配慮について正確に理解してもらうのが難しい場合もあります。可能であれば、主治医に相談し、症状や業務上で配慮が必要な点について意見書を書いてもらうのも有効な方法です。客観的な専門家の意見があることで、会社側も状況を把握しやすくなり、具体的な対応を検討しやすくなります。
- 落ち着いて話せる環境とタイミングを選ぶ 立ち話や、相手が忙しそうな時間帯に切り出すのは避けましょう。「少しご相談したいことがあるので、お時間をいただけますか」と事前にアポイントを取り、会議室など他の人に話を聞かれない、落ち着いた環境で話すことが望ましいです。
自分の障がいについて話すことは、勇気がいることです。しかし、一人で抱え込まずに周囲の理解を得ることは、孤立を防ぎ、自分自身が働きやすい環境を主体的に作っていくための大切な一歩となります。
自分に合った働き方を見つける
「自分に合った働き方」と言っても、その形は一人ひとり異なります。症状の特性や程度、大切にしたい価値観、体力などを総合的に考え、自分だけのバランスを見つけていくプロセスが重要になります。
画一的な正解を求めるのではなく、多様な選択肢の中から、今の自分にとって最も心地よいと感じられる働き方を探してみましょう。
■働き方の選択肢を広げる 一つの働き方に固執せず、視野を広げることで、可能性が見えてくることがあります。
- 雇用形態を柔軟に考える 正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなど、さまざまな雇用形態があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。
| 雇用形態 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用が安定している、福利厚生が充実している | 業務上の責任が重い傾向、異動や転勤の可能性がある |
| 契約・派遣社員 | 業務範囲が明確、契約期間が決まっている、残業が少ない傾向 | 雇用期間が定められている、正社員と比べて待遇が異なる場合がある |
| パート・アルバイト | 勤務時間や日数の融通がききやすい、未経験から始めやすい | 収入が不安定になりやすい、福利厚生が限定的な場合がある |
- 勤務形態や環境を選ぶ フルタイムでの勤務が難しい場合は、時短勤務や週3〜4日勤務といった選択肢も考えられます。また、通勤やオフィス環境に強いストレスを感じる場合は、在宅勤務(リモートワーク)が可能な仕事を探すのも有効な手段です。
- 障害者雇用枠を活用する 精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は、障害者雇用枠での就職も選択肢に入ります。一般枠に比べて、症状や特性への理解が得やすく、必要な配慮を受けながら働きやすいというメリットがあります。
■自分自身を深く理解する どのような働き方が合うかを見つけるためには、まず自分自身を客観的に理解することが不可欠です。以下の点について、一度じっくりと考えてみる時間を持つのもよいでしょう。
- どのような状況や環境だと不安が強まるか
- 逆に、どのような状況だと比較的穏やかな気持ちでいられるか
- 仕事に求めるものの優先順位は何か(例:給与、やりがい、安定、人間関係、ワークライフバランス)
- 無理なく働ける1日の活動時間や、週の勤務日数はどのくらいか
- どのようなサポートや配慮があれば、安心して業務に取り組めそうか
■試行錯誤を恐れない 最初から完璧な職場や働き方を見つけるのは、簡単なことではありません。まずは短時間のアルバイトから始めてみる、就労移行支援事業所の実習制度を利用してみるなど、「試してみる」という姿勢も大切です。
もし「この働き方は合わないな」と感じたとしても、それは失敗ではありません。自分に合わないものが分かったという、次につながる貴重な経験です。焦らず、自分自身の心と体の声に耳を傾けながら、少しずつ自分にとって心地よい働き方を探求していくことが、長く仕事を続けていくための鍵となります。
まとめ
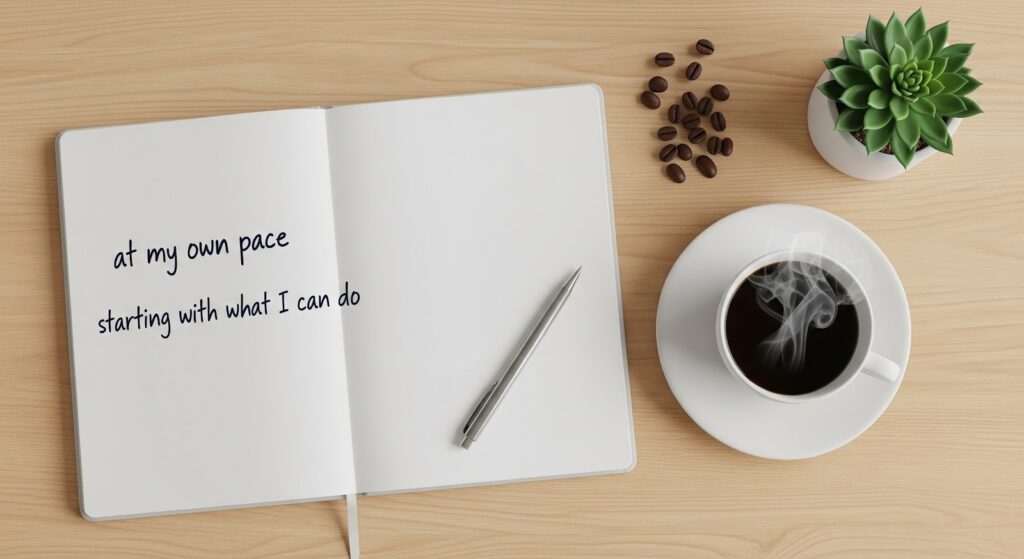
本記事では、不安症(不安障がい)の基本的な知識から、仕事で直面する困難、そしてその対処法や利用できる支援制度までを幅広く解説しました。
不安症は、けっして特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。その症状によって仕事に支障が出ることはありますが、それは本人の能力や意欲の問題ではありません。重要なのは、不安症の特性を正しく理解し、適切な対処法を講じることです。
最後に、これまでの内容の要点をまとめます。
- 症状の正しい理解とセルフケア まずは、不安症がどのようなものかを知り、治療やセルフケアに取り組むことが基本です。生活リズムを整え、心身の安定を図ることが、働く上での土台となります。
- 自分に合った環境を選ぶ・作る ご自身の特性を理解し、症状を誘発しにくい仕事や職場環境を選ぶことが大切です。また、今の職場で働き続けるためには、合理的配慮を求めるなど、働きやすい環境を主体的に作っていく視点も有効です。
- 一人で抱え込まず、支援を活用する 医療機関はもちろん、就労移行支援事業所やハローワーク、地域障害者職業センターなど、専門的なサポートを提供してくれる機関は数多く存在します。一人で悩まず、これらの支援を積極的に活用することが、状況を改善する近道となります。
- 焦らず、自分だけのペースを見つける 最適な働き方は人それぞれ異なります。正解を一つに絞ろうとせず、雇用形態や勤務形態など多様な選択肢の中から、今の自分にとって無理のないペースやバランスを見つけていくことが、長く働き続けるための鍵となります。
不安と向き合いながら働く道のりは、平坦ではないかもしれません。しかし、適切な知識とサポートを得ながら、ご自身の特性に合った工夫を重ねていくことで、自分らしいキャリアを築いていくことは十分に可能です。
カチカでは、障害を持つ方が自分のペースで短時間から始められる作業や特性を最大限に活かせるクリエイティブな仕事を通じて、「自分に合った持続可能な働き方」 を見つけるお手伝いをいたします。
あなたの特性と上手く付き合っていくための具体的な一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。