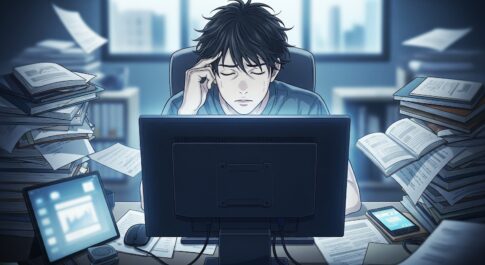この記事では、ADHDの特性と向き合いながら働く方が、ご自身の能力を最大限に発揮し、集中力の困難さを乗り越えていくための、具体的な対策とヒントを網羅的に解説します。 「なぜか集中できない」という漠然とした悩みを、実現可能な行動プランへと変えるために。
この記事を最後まで読むことで、以下の点が明確になります。
- ADHDの「不注意・多動性・衝動性」という特性が、仕事の集中力にどう影響するのか、その根本的な理由
- 困難さの裏返しでもある、ADHDの特性が持つ「強み」と、それを活かすための視点
- 出勤前から仕事中まで、明日からすぐに実践できる具体的な集中力対策やタスク管理術
- 一人で抱え込まずに頼れる、専門家や公的な支援機関とその活用方法
この記事は、ご自身の特性と向き合い、より良い働き方を模索している、以下のような方々に向けて執筆しています。
- 「やる気がない」「怠けている」と誤解されがちで、自己嫌悪に陥っている方
- ケアレスミスや忘れ物、タスクの先延ばしが多く、仕事で悩んでいる方
- 周囲の音や刺激が気になり、なかなか目の前の業務に集中できない方
- 自分のADHD特性を正しく理解し、弱みをカバーしながら強みを活かせる働き方を見つけたい方
この記事が、集中できないという悩みから抜け出し、自分らしいパフォーマンスを発揮するための、信頼できる道しるべとなれば幸いです。
Contents
ADHD(注意欠如・多動症)とは?理解を深める

ADHDの特徴と症状
ADHD(注意欠如・多動症)の主な特徴は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つに分けられます。これらの特性の現れ方やその強さには個人差があり、年齢やおかれている環境によっても変化します。
主な特徴と、それに伴う具体的な症状の例を以下に示します。
| 主な特徴 | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 不注意 (集中力を持続させたり、注意を維持したりすることが難しい) | ・仕事や作業でケアレスミスをしやすい・集中力が続かず、気が散りやすい・忘れ物や失くしものが多い・話しかけられても、聞いていないように見えることがある ・整理整頓や、物事を順序立てて行うことが苦手 |
| 多動性 (状況に合わない過剰な活動性や落ち着きのなさ) | ・静かに座っていることが苦手で、そわそわと体を動かす・貧乏ゆすりなど、手足を絶えず動かしている・静かにすべき場面でおしゃべりが止まらなくなる ※大人の場合は、内面的な落ち着きのなさや焦燥感として現れることもあります。 |
| 衝動性 (考えよりも先に行動してしまう傾向) | ・相手の話が終わる前に、さえぎって話し始めてしまう・順番待ちなどが苦手・思いついたことを深く考えずに発言・行動してしまう ・衝動買いをしてしまうことがある |
これらの特性の現れ方によって、ADHDは以下の3つのタイプに分類されます。
- 不注意優勢型:不注意の症状が特に目立つタイプです。
- 多動・衝動性優勢型:多動性と衝動性の症状が特に目立つタイプです。
- 混合型:不注意、多動性、衝動性の3つの症状が、いずれも同じように現れるタイプです。
これらの症状は誰にでもある程度見られるものですが、ADHDの場合はその程度が強く、社会生活や日常生活においてさまざまな困難が生じている状態を指します。
ADHDの強みと弱み
ADHDの特性は、日常生活や仕事において困難さ(弱み)として現れることがある一方で、状況や環境によっては大きな強みにもなり得ます。特性は一つの側面だけでなく、多角的に捉えることが理解を深める鍵となります。
ADHDの主な特性が、それぞれどのような強み・弱みとして現れるか、その例を以下に示します。これらは、いわば同じ特性の表裏の関係にあると考えることができます。
| 特性 | 強みとして現れる側面 | 弱みとして現れる側面 |
|---|---|---|
| 不注意 | ・好奇心旺盛で、様々なことに関心を持つ・独創的、クリエイティブな発想が得意・興味のある分野には驚異的な集中力(過集中)を発揮する ・既成概念にとらわれない柔軟な思考ができる | ・注意が散漫になりやすく、集中力が持続しにくい・ケアレスミスや忘れ物が多い・物事の段取りを立てたり、整理整頓したりすることが苦手 ・複数のタスクを同時に進めることが難しい |
| 多動性 | ・エネルギッシュで行動力がある・フットワークが軽く、すぐに行動に移せる・新しいことにも物怖じしない ・単調な作業にも飽きずに取り組めることがある | ・静かな場所でじっとしていることが苦痛・そわそわして落ち着きがないように見える・会議中などに貧乏ゆすりなどをしてしまう ・過度なおしゃべりをしてしまうことがある |
| 衝動性 | ・決断力があり、判断が速い・チャレンジ精神が旺盛・率直で裏表がない ・場の空気を明るくするムードメーカーになることがある | ・深く考えずに行動・発言してしまうことがある・相手の話を最後まで聞かずに話し始めてしまう・順番を待つことが苦手 ・感情のコントロールが難しく、カッとなりやすい |
このように、ADHDの特性は必ずしもネガティブなものだけではありません。自分の特性を正しく理解し、強みを活かせる環境を見つけたり、弱みに対しては具体的な対策を講じたりすることで、困難を軽減し、能力を発揮しやすくなります。自分自身を責めるのではなく、特性との付き合い方を工夫していくことが大切です。
集中できない理由とその背景

ADHDの特性がもたらす集中力の低下
ADHDの方が仕事などで「集中できない」と感じるのは、本人の意思や努力が足りないからではなく、脳の特性に由来するものです。ADHDの主な特徴である「不注意」「多動性」「衝動性」が、それぞれ集中力の維持に影響を与えています。
- 不注意特性の影響 集中力の低下に最も直接的に関わるのが、この不注意特性です。周囲の音や光、人の動きといった外部からの刺激に意識が向きやすく、また、頭の中に次々と別の考えが浮かんでくるなど、内部からの刺激によっても注意が逸れがちになります。特に、関心を持てない単調な作業では注意を持続させることが難しくなります。その一方で、興味のあることに対しては「過集中」と呼ばれる非常に高い集中力を発揮することもあります。
- 多動性特性の影響 じっと座っていることへの苦手意識や、そわそわと体を動かしていたいという内的な欲求が、デスクワークなどの集中を妨げる一因となります。大人のADHDの場合、目に見える動きよりも「頭の中が常に忙しい」「思考が絶えず動き回っている」といった内面的な多動性として現れることも少なくありません。これにより、一つの物事に思考を集中させることが難しくなります。
- 衝動性特性の影響 「今すぐこれをやりたい」という思いつきや欲求を抑えることが難しく、本来やるべきタスクよりも新しい刺激を優先してしまう傾向があります。例えば、仕事中に気になったことをすぐに調べ始めたり、別のアイデアに飛びついてしまったりすることで、集中が途切れてしまうことがあります。この特性は、長期的な視点で計画的に物事を進める上での妨げとなる場合があります。
これらの特性はそれぞれが独立しているわけではなく、互いに影響し合うことで集中力の維持をより難しくさせています。こうした背景を理解することが、自分に合った対策を見つけるための第一歩となります。
職場環境や人間関係の影響
ADHDの特性による集中力の問題は、個人の内的な要因だけでなく、職場環境や人間関係といった外的な要因によっても大きく左右されることがあります。ADHDの方が能力を発揮するためには、本人の努力だけでなく、環境との相互作用を理解することが重要になります。
■職場環境が与える影響 ADHDの特性を持つ方にとって、刺激の多い環境は集中力を維持する上で大きな障壁となることがあります。特に以下のような環境は、注意が散漫になりやすい傾向を強める可能性があります。
- 物理的な環境からの刺激
- オープンスペースのオフィス:周囲の話し声、電話の音、人の往来などが常に意識に入り、集中が途切れやすくなります。
- 多くの視覚情報:壁に貼られた多くのポスターや、整理されていないデスク周りなど、視界に入る情報が多いと注意が逸れる原因になります。
- 感覚的な刺激:強すぎる照明、不快な室温、特定の匂いなど、感覚過敏の特性がある場合は、これらが持続的なストレスとなり集中力を削ぎます。
- 業務の進め方による影響
- 頻繁な割り込み:急な指示や想定外の業務が頻繁に発生すると、思考が中断され、元のタスクに集中を戻すことが難しくなります。
- 曖昧な指示:何をすべきか、ゴールはどこかが不明確だと、思考がまとまらず、作業に着手しにくくなります。
- マルチタスクの要求:複数の作業を同時にこなすことは、注意の切り替えが苦手なADHDの特性を持つ方にとって、特に負荷が高くなります。
■人間関係が与える影響 職場での人間関係から生じるストレスや悩みも、集中力を低下させる大きな要因です。ADHDの特性から、意図せずコミュニケーションのすれ違いが生じ、心理的な負担を抱えてしまうことがあります。
- コミュニケーション上の悩み
- 衝動的な発言で相手を傷つけてしまったかもしれないという不安。
- ケアレスミスや忘れ物を繰り返し指摘され、自信をなくしてしまう。
- 相手の話に集中できず、上の空に見えてしまうことへの申し訳なさ。
- 評価に対する不安
- 「やる気がない」「怠けている」と誤解されているのではないかという恐れ。
- 周囲のペースについていけないことへの焦りや劣等感。
こうした心理的なストレスは、脳のワーキングメモリ(情報を一時的に保持し、処理するための能力)に大きな負荷をかけます。その結果、本来仕事のタスクに向けるべき認知的なリソースが、不安や悩みの処理に奪われてしまい、集中力の低下につながるのです。
このように、集中できない背景には、個人の特性と環境とのミスマッチが存在していることが少なくありません。
プライベートの悩みが仕事に与える影響
仕事のパフォーマンスは、職場だけの問題で完結するわけではありません。プライベートでの悩みやストレスも、私たちの集中力や意欲に大きな影響を与えます。特にADHDの特性を持つ方は、その特性がプライベートでの悩みを引き起こしやすく、また、仕事への影響もより顕著に現れることがあります。
ADHDの特性は、日常生活の様々な場面で困難さとして現れることがあり、これらがプライベートにおける悩みの種となるケースは少なくありません。
- 人間関係の悩み:衝動的な発言でパートナーや友人を傷つけてしまったり、相手の話を遮ってしまったりすることで、関係がこじれてしまうことがあります。また、感情の波が大きく、些細なことで激しく落ち込んだり怒ったりすることも、対人関係のストレスにつながります。
- 金銭的な悩み:衝動買いを繰り返してしまったり、計画的にお金を使うことが苦手だったりするため、金銭的な問題を抱えやすくなります。
- 生活管理の悩み:公共料金の支払いや重要な手続きを忘れてしまう、部屋が片付けられないといった「不注意」特性からくる問題は、自己嫌悪や生活上の具体的なトラブルにつながり、大きなストレスとなります。
こうしたプライベートの悩みが常に頭の中を占めている状態は、脳のワーキングメモリ(情報を一時的に記憶し処理する能力)に大きな負荷をかけます。ワーキングメモリの容量が悩みで圧迫されると、仕事に必要な情報を処理するためのリソースが不足し、以下のような影響が現れます。
- 目の前のタスクに意識を向けることが難しくなり、上の空になってしまう
- 通常ならしないような単純なミスが増加する
- 思考がまとまらず、的確な判断や迅速な決断ができない
- 精神的な疲労感が抜けず、仕事へのモチベーションが低下する
また、ADHDの特性の一つに、思考の切り替えが苦手という側面があります。そのため、一度プライベートの悩みにとらわれると、勤務時間中もそのことが頭から離れず、考え込んでしまう「反芻思考」に陥りやすくなります。仕事に集中しようとしても、無意識に悩みに思考が引き戻されてしまうため、集中力の維持が非常に困難になるのです。
このように、仕事中の集中力を考える上では、仕事の環境やタスクだけでなく、プライベートで抱えている問題が心身に与える影響も無視できません。心穏やかに過ごせる時間を確保することも、安定したパフォーマンスを維持するためには重要な要素といえるでしょう。
出勤前の準備と対策

朝のルーチンを整える
ADHDの特性を持つ方にとって、朝の時間は特に困難を感じやすい時間帯かもしれません。脳がまだ完全に覚醒していない状態で、身支度や持ち物の準備など、多くのタスクをこなす必要があるため、注意が散漫になったり、段取りがうまくいかなかったりすることがあります。
このような朝の混乱を軽減し、スムーズな一日をスタートさせるために有効なのが、「朝のルーチンを整える」ことです。毎回「次は何をしようか」と考えるのではなく、一連の行動を習慣化することで、脳のワーキングメモリへの負担を減らし、無意識に近い形で行動できるようになります。
自分に合った朝のルーチンを作るためのポイントをいくつかご紹介します。
- 行動をシンプルにする 最初から完璧なルーチンを目指す必要はありません。「起きたらまず水を飲む」「着替える」など、ごく簡単なタスクから始め、それを確実にこなすことから習慣づけていきましょう。タスクを詰め込みすぎないことが、継続の鍵となります。
- 行動の順番を決めておく 「歯を磨いたら、顔を洗う」「朝食を食べたら、薬を飲む」というように、「Aをしたら、次はBをする」という流れを固定します。これにより、次の行動を思い出す手間が省け、行動がスムーズにつながるようになります。
- 時間を見える化する 時間の感覚を掴むのが苦手な場合は、タイマーを活用するのが効果的です。「10分で着替えと洗顔を済ませる」など、タスクごとに時間を区切ると、集中しやすくなります。残り時間が視覚的にわかるタイマーもおすすめです。
- チェックリストを活用する やるべきことを紙に書き出し、目につく場所(洗面所や玄関のドアなど)に貼っておきましょう。一つひとつのタスクを完了するたびにチェックを入れることで、やり忘れを防げるだけでなく、達成感も得られます。
- 余裕を持った時間設定 予定通りに進まないことも想定し、スケジュールには十分なバッファを持たせましょう。ギリギリの時間設定は焦りを生み、ケアレスミスや忘れ物の原因となります。理想の起床時間よりも15分早く起きるだけでも、心に大きな余裕が生まれます。
朝のルーチン例
- 決まった時間に起床する
- カーテンを開けて太陽の光を浴びる
- 着替えを済ませる(前夜のうちに準備しておく)
- 洗顔・歯磨き
- 簡単な朝食をとる
- 持ち物チェックリストで確認する
- 決まった時間までに家を出る
自分に合ったルーチンは、試行錯誤を繰り返しながら見つかるものです。うまくいかない日があっても自分を責めず、一つでもできたら良しとするくらいの気持ちで、少しずつ取り組んでみてください。
出勤前にできる心の準備
バタバタと過ぎていく朝の時間ですが、物理的な準備だけでなく、心の状態を整えることも、日中の集中力を保つ上で大切な要素となります。特にADHDの特性を持つ方は、過去の失敗体験や仕事へのプレッシャーから、出勤前に不安や憂鬱な気持ちを抱えやすい傾向があります。
ここでは、出勤前に短時間でできる心の準備をいくつかご紹介します。これらは、一日の始まりに心の負担を軽くし、少しでも穏やかな気持ちで仕事に向かうための工夫です。
- その日の目標を「一つだけ」決める 「あれもこれもやらなければ」と考えると、圧倒されてしまい、かえって行動できなくなることがあります。出勤前や通勤中に、その日達成したい最も重要な目標を一つだけ決めてみましょう。「〇〇の資料を完成させる」「△△さんに報告する」など、具体的で達成可能な目標が良いでしょう。目標を絞ることで、一日の行動の軸が定まり、思考が分散しにくくなります。
- ポジティブな自己暗示 「またミスするかもしれない」といったネガティブな思考が浮かびやすい場合は、意識的に肯定的な言葉を自分にかけることが有効です。「今日は大丈夫」「一つずつ丁寧に取り組もう」「困ったら相談しよう」など、自分を安心させる言葉を心の中で繰り返します。これは、不安を軽減し、自己肯定感を支える助けになります。
- 短時間のマインドフルネス(瞑想) 家を出る前に1〜3分ほど、静かに座って自分の呼吸に意識を向ける時間を作ります。頭の中に様々な考えが浮かんできても、それを追いかけずに「ただ呼吸している自分」に意識を戻すことを繰り返します。これにより、忙しく動き回る思考を一度リセットし、心を落ち着かせることができます。
- 五感を使って気分を切り替える 好きな音楽を聴きながら準備をする、お気に入りのアロマを少しだけ香る、肌触りの良い服を選ぶなど、自分の「心地よい」と感じる感覚を意識的に取り入れるのも良い方法です。心地よい刺激は、気分を前向きに切り替えるスイッチの役割を果たしてくれます。
これらの準備は、毎日完璧に行う必要はありません。その日の自分の状態に合わせて、できそうなものを一つでも試してみるというくらいの気持ちで取り入れてみてください。自分なりの「心の整え方」を見つけることが、安定したパフォーマンスにつながっていきます。
必要な持ち物の整理と確認
ADHDの「不注意」特性は、忘れ物や失くしものの多さとして現れることがあります。「家を出る直前に鍵が見つからない」「会社に着いてから重要な書類を忘れたことに気づく」といった経験は、大きな焦りや自己嫌悪につながり、その日一日の仕事への集中力にも影響を及ぼしかねません。
こうした事態を防ぎ、安心して一日を始めるためには、持ち物を整理し、確認する仕組みを作ることが効果的です。
準備は前日の夜に行う習慣を 朝の時間は、脳がまだ完全に目覚めていない上、時間的な制約もあるため、冷静な判断がしにくい状態です。忘れ物を防ぐ最も確実な方法は、比較的落ち着いて時間の取れる前日の夜に、翌日の準備を済ませておくことです。
- 翌日のスケジュールを確認し、必要な書類や道具を準備する
- 仕事で着ていく服を選んでおく
- カバンに必要なものを全て入れておく
天気予報を確認し、傘が必要かどうかを判断しておくことも、朝の小さなストレスを減らすのに役立ちます。
持ち物の「定位置」を決める 「どこに置いたか分からない」という状況をなくすため、全ての持ち物に決まった置き場所、つまり「定位置」を設けましょう。
- 玄関周り:鍵、定期入れ、社員証などは、玄関のトレーやフックにかける
- カバンの中:財布は内ポケット、スマートフォンは外側のポケットなど
- 自室:充電器やイヤホンはデスクの特定の引き出しに
物を使い終わったら必ず定位置に戻すことを意識することで、「探す」という行為に費やす時間と精神的なエネルギーを大幅に削減できます。
チェックリストの徹底活用 記憶に頼るのではなく、視覚的に確認できるチェックリストを用いることは、ワーキングメモリへの負担を減らし、忘れ物を防ぐ上で非常に有効な手段です。
- 固定リストと変動リスト:毎日必ず持っていくもの(財布、鍵など)を「固定リスト」として、日によって変わるもの(PC、書類、折りたたみ傘など)を書き込める「変動リスト」のスペースを設けると便利です。
- 設置場所:リストは、玄関のドアや靴箱の上など、家を出る前に必ず目に入る場所に貼り出しておきましょう。
- ツールの活用:スマートフォンのリマインダー機能やチェックリストアプリを活用するのも良い方法です。決まった時間に通知が来るように設定しておけば、確認漏れを防げます。
カバンの中を整理する カバンの中に物を無造作に入れると、いざという時に必要なものが見つからず、混乱の原因になります。バッグインバッグやポーチを活用し、カバンの中を構造化しましょう。
- カテゴリ分け:文房具、充電器などのガジェット類、化粧品など、種類ごとにポーチを分けて収納します。
- 視認性の高いポーチ:中身が一目でわかる透明やメッシュ素材のポーチを選ぶと、何が入っているかを確認しやすくなります。
これらの工夫は、単に忘れ物をなくすだけでなく、「準備ができている」という安心感をもたらし、落ち着いた気持ちで仕事に向かうための大切な土台となります。仕事中に実践できる集中力向上の対策
仕事中に実践できる集中力向上の対策

短時間集中法の活用
ADHDの特性として、長時間の集中を持続させることが難しいという側面があります。しかし、これは「全く集中できない」ということではなく、「集中の波をコントロールしにくい」状態と捉えることができます。この特性を踏まえると、長時間連続して作業するのではなく、意図的に短い時間に区切って集中と休憩を繰り返す「短時間集中法」が非常に有効です。
これは、集中力が途切れやすいという特性を弱みと捉えるのではなく、短距離走を繰り返すような働き方へと切り替えることで、特性を活かすアプローチといえます。
代表的な手法:ポモドーロ・テクニック 短時間集中法の中でも広く知られているのが「ポモドーロ・テクニック」です。具体的な手順は以下の通りです。
- 取り組むタスクを決める
- タイマーを25分にセットする
- タイマーが鳴るまで、脇目もふらずそのタスクだけに集中する(途中で他のことが気になってもメモだけして後回しにする)
- タイマーが鳴ったら、5分間の短い休憩をとる
- 上記1〜4を1セット(1ポモドーロ)とし、4セット繰り返したら15〜30分程度の長めの休憩をとる
この手法には、以下のようなメリットがあります。
- 心理的ハードルの低下:「25分だけなら頑張れる」と感じられ、タスクに取りかかりやすくなります。
- 集中力の維持:定期的な休憩が脳をリフレッシュさせ、次の集中へのエネルギーを回復させます。
- 時間管理能力の向上:「このタスクには2ポモドーロ必要」といったように、作業時間の見積もりがしやすくなります。
自分に合った方法を見つける ポモドーロ・テクニックの「25分+5分」という時間はあくまで目安です。人によっては「15分集中+3分休憩」の方が合っているかもしれませんし、作業内容によっては「45分集中+10分休憩」が適している場合もあります。
大切なのは、自分自身の集中力が自然に続く時間を見極め、それに合わせて時間をカスタマイズすることです。キッチンタイマーやスマートフォンのアプリなど、残り時間が視覚的にわかるツールを使うと、より取り組みやすくなります。
休憩時間には、スマートフォンでSNSを見るなど脳に刺激を与えるものではなく、ストレッチをする、お茶を飲む、窓の外を眺めるなど、心身をリラックスさせることを意識すると、次の集中にスムーズに移行しやすくなります。
環境を整えるための工夫
ADHDの特性を持つ方は、周囲の音や視界に入る情報といった外部からの刺激に影響を受けやすく、それが集中力の低下につながることがあります。意思の力だけで集中しようとするのではなく、集中しやすい環境を物理的に作り出す工夫が非常に効果的です。
ここでは、職場で実践できる環境整備の工夫をいくつかご紹介します。
- 視覚からの刺激を減らす 意図しない情報が視界に入ることを防ぎ、目の前のタスクに意識を向けやすくします。
- デスク周りの整理:机の上には、現在使っている仕事道具以外は置かないようにします。書類はファイルボックスに立てて収納し、小物は引き出しにしまうなど、視界に入る物の数を最小限に抑えます。
- 視界を物理的に遮る:可能であれば、パーテーションを設置してもらったり、デスクを壁側に向けて配置を変えたりすることで、人の動きなどが気になりにくくなります。
- デジタル環境の整理:パソコンのデスクトップ上のアイコンは最小限にし、壁紙はシンプルなものを選びます。作業中は不要なアプリケーションやブラウザのタブを閉じることを徹底します。
- 聴覚からの刺激を遮断する 周囲の話し声や物音による集中の中断を防ぎます。
- ノイズキャンセリング機能の活用:ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンは、周囲の雑音を効果的に低減してくれます。音楽を流さず、ノイズキャンセリング機能だけを使うのも一つの方法です。
- 環境音(ホワイトノイズ)の利用:雨音や川のせせらぎといった単調な環境音を小さな音量で流すことで、気になる会話や突発的な物音をマスキングする効果が期待できます。
- 耳栓の活用:シンプルですが、物理的に音を遮断する効果的なツールです。
- 割り込みをコントロールする 集中している時間帯を確保し、思考の中断を防ぐための工夫です。
- 「集中タイム」の表明:「今は集中します」といった表示プレートをデスクに置いたり、チャットツールのステータスを変更したりして、話しかけないでほしい時間帯であることを周囲に伝えます。
- 通知のオフ:集中したいと決めた時間は、メールやチャット、スマートフォンの通知をオフにします。これにより、予期せぬ通知で意識が逸れるのを防ぎます。
これらの工夫は、すべてを一度に行う必要はありません。まずはご自身の職場環境で試せそうなことから一つずつ取り入れて、自分にとって最も集中しやすい環境を見つけていくことが大切です。内容によっては職場の理解や協力が必要な場合もあるため、上司や同僚に相談してみることも検討しましょう。
タスク管理の方法とツール
ADHDの特性として、やるべきことが頭の中で整理しきれなかったり、何から手をつければ良いか分からなくなったり、重要なタスクをうっかり忘れてしまったりすることがあります。これは、情報を一時的に記憶し処理する「ワーキングメモリ」に負荷がかかりやすいことに起因します。
タスク管理は、この頭の中の情報を外部に記録し整理することで、ワーキングメモリの負担を軽減し、安心して仕事を進めるための非常に有効な手段です。
タスク管理の基本的なステップ まずは、タスクを整理するための基本的な流れを理解することが大切です。
- すべて書き出す(ブレインダンプ) まずは、頭の中にある「やること」を、大小問わずすべて紙やツールに書き出します。「〇〇さんにメールする」といった小さなことから、「△△の企画書をまとめる」といった大きなことまで、区別せずに洗い出すことで、頭の中が整理され、漠然とした不安感を軽減できます。
- 細かく分解する(タスクの細分化) 「企画書をまとめる」のような大きなタスクは、どこから手をつけていいか分からず、先延ばしの原因になりがちです。これを、「関連資料を集める」「構成案を作る」「上司に相談する」といった、具体的で短時間で実行可能な小さなステップ(ベビーステップ)に分解します。一つひとつのタスクが明確になることで、行動へのハードルが大きく下がります。
- 優先順位をつける 書き出したタスクに優先順位をつけます。複雑な方法である必要はなく、「今日必ずやること」「今週中にやること」といったシンプルな分類でも構いません。視覚的に分かりやすくするために、色分けするのも効果的です。
自分に合ったツールを見つける タスク管理ツールには、手軽に始められるアナログなものから、多機能なデジタルツールまで様々です。それぞれの特徴を理解し、ご自身が「続けやすい」と感じるものを選ぶことが最も重要です。
| ツールの種類 | 特徴とメリット | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| アナログツール (手帳、ノート、付箋など) | ・手で書くことで記憶に定着しやすい・電源やアプリの起動が不要ですぐに使える・レイアウトの自由度が高い ・付箋は貼り替えが可能で、進捗管理がしやすい | ・デジタル機器の操作が苦手な方・自分のペースで自由に書き込みたい方 ・PCの画面とは別に、常にタスクを視界に入れておきたい方 |
| デジタルツール (ToDoリストアプリ、カレンダーアプリなど) | ・リマインダー機能で抜け漏れを防げる・スマートフォンやPCなど複数の端末で同期できる・繰り返しタスクの設定が簡単 ・完了したタスクの記録が残りやすい | ・スマートフォンを常に持ち歩いている方・通知機能でタスクを思い出したい方 ・タスクの並べ替えや修正を頻繁に行う方 |
ツールの具体例
- ToDoリストアプリ:Microsoft To Do、Todoist など
- かんばん方式ツール:Trello など(「未着手」「進行中」「完了」のようにタスクの状況を視覚的に管理)
- カレンダーアプリ:Google Calendar など(タスクを特定の時間枠に予定として組み込む「タイムブロッキング」に有効)
完璧なタスク管理を目指す必要はありません。まずは一つのツールを試してみて、うまくいかなければ別の方法を試す、というくらいの気持ちで始めてみましょう。タスク管理は自分を縛るためのものではなく、安心して仕事に取り組むためのサポーターと捉えることが、継続の秘訣です。
集中できないと感じたときの相談先

専門家に相談するメリット
仕事に集中できないという悩みや、ADHDの特性による困難さが大きい場合、自分一人で対策を講じることには限界があるかもしれません。そのような時、医師やカウンセラーといった専門家に相談することは、状況を改善するための有効な選択肢となります。専門家への相談には、主に以下のようなメリットがあります。
- 的確な診断と自己理解の深化 専門家による客観的な評価を通じて、自身の困難さの背景にADHDの特性がどのように関わっているのかを正しく理解することができます。「自分の努力が足りないからだ」といった自己否定から抜け出し、特性に基づいた適切な捉え方ができるようになることは、大きな第一歩です。
- 自分に合った対策の提案 専門家は、個々の特性の現れ方や仕事内容、生活環境などを踏まえた上で、パーソナライズされた具体的なアドバイスを提供してくれます。環境調整の工夫やスキルトレーニング、必要に応じた薬物療法など、医学的・心理学的な知見に基づいた多様な選択肢の中から、自分に合った対処法を見つける手助けとなります。
- 二次的な問題への対応 ADHDの困難さが長期間続くと、それが原因でうつ病や不安障害といった二次的な心の問題を引き起こしたり、失敗体験の繰り返しから自己肯定感が著しく低下したりすることがあります。専門家はこうした併存する問題にも気づき、適切な治療やカウンセリングにつなげることができます。
- 利用可能な支援制度への橋渡し 診断を受けることで、障害者手帳の取得や就労移行支援、その他様々な福祉サービスなど、利用できる公的な支援の道が開ける場合があります。専門家は、どのような制度が利用可能かといった情報を提供し、必要な手続きをサポートする役割も担っています。
- 心理的な負担の軽減 一人で悩みを抱え込まず、専門知識を持つ第三者に話を聞いてもらうだけでも、心理的な負担は大きく軽減されます。自分の困難さを理解してくれる存在がいるという安心感は、前向きに取り組んでいくための大切な支えになります。
専門家への相談は、決して特別なことではありません。自分自身の特性と上手く付き合い、より良い働き方や生活を見つけるための、積極的で建設的な一歩と捉えることができます。
支援機関の活用方法
医療機関での相談に加え、仕事や生活に関する具体的なサポートを提供してくれる公的な支援機関を活用することも、困難を乗り越えるための有効な手段です。これらの機関は、ADHDを含む発達障害のある方が安定して働き続けるための、専門的な知識とノウハウを持っています。
相談は無料でできる場合がほとんどで、診断がなくても相談に応じてくれる機関もあります。一人で抱え込まず、まずはどのようなサポートが受けられるのか、情報を集めることから始めてみるのも良いでしょう。
主な支援機関とその役割 仕事に関する悩みに対応してくれる代表的な支援機関には、以下のようなものがあります。それぞれに役割や特徴があるため、ご自身の状況や目的に合わせて相談先を検討することが大切です。
| 支援機関の名称 | 主な役割と特徴 |
|---|---|
| 発達障害者支援センター | ・地域における発達障害支援の中核的な機関。・本人や家族からの様々な相談に応じ、適切な関係機関へつなぐ役割も担う。 ・どこに相談して良いか分からない場合の、最初の相談窓口として適している。 |
| 地域障害者職業センター | ・ハローワークと連携し、専門的な職業リハビリテーションを提供する。 ・職業能力の評価、職業準備支援、職場復帰支援(リワーク支援)など、個別のプログラムが充実している。 |
| ハローワーク(障害者専門窓口) | ・障害の特性に配慮した職業相談や職業紹介を行う。 ・障害のある方を対象とした求人の情報提供や、就職活動のサポートを受けられる。 |
| 就労移行支援事業所 | ・一般企業への就職を目指す障害のある方が利用できる福祉サービス。 ・職業訓練、職場探し、職場定着支援など、就職に必要なスキル習得から就職後までを一貫してサポートする。 |
| 障害者就業・生活支援センター (なかぽつ) | ・就職後のサポートに重点を置いている。 ・仕事上の悩みだけでなく、金銭管理や健康管理といった生活面での相談にも応じ、安定した職業生活を継続できるよう支援する。 |
支援機関を上手に活用するためのポイント 支援をより効果的に受けるためには、いくつか心に留めておくと良い点があります。
- 自分の状況を具体的に伝える 相談の際には、「何に困っているのか」「どのような時に集中できないのか」「得意なこと、苦手なことは何か」「どのような働き方を希望しているか」などを、できるだけ具体的に伝えることが大切です。事前にメモなどにまとめておくと、落ち着いて話をしやすくなります。
- 一つの機関で解決しようとしない 上記の機関は、それぞれが連携を取り合って支援を行っています。最初の相談先で全ての悩みが解決しなくても、そこからさらに適切な機関を紹介してもらえるケースが多いため、焦る必要はありません。
- 受け身にならず、主体的に関わる 支援機関はあくまでサポーターです。提案された対策を試してみた結果どうだったか、自分はこうしたいという希望はあるかなど、自身の考えや状況をフィードバックすることで、より自分に合った支援へとつながっていきます。
これらの支援機関は、ADHDの特性と付き合いながら自分らしく働くための、頼れるパートナーとなり得ます。一人で悩まず、専門的なサポートを活用する選択肢があることを知っておくことが重要です。
まとめ

ADHDの特性による集中力の困難さは、個人の意思や努力の問題ではなく、脳の特性と、職場やプライベートなどの環境との相互作用に起因します。そのため、自分を責めるのではなく、特性への正しい理解に基づいた対策を講じることが重要です。
まず自身のADHD特性を深く理解し、それが状況によって強みにも弱みにもなり得ることを知ることが第一歩です。その上で、朝のルーチンを整える、ポモドーロ・テクニックのような短時間集中法を取り入れる、タスクを細分化して管理する、物理的な環境を調整して刺激を減らすといった、日々の具体的な工夫を試していくことが有効といえるでしょう。
一人で抱え込むのが難しいと感じたときには、決して無理をする必要はありません。医師やカウンセラーといった専門家、あるいは発達障害者支援センターや就労移行支援事業所といった公的な支援機関に相談し、客観的なアドバイスやサポートを得ることも大切な選択肢となります。
完璧を目指すのではなく、試行錯誤を繰り返しながら、ご自身に合った対策や周囲との付き合い方を見つけていくことが、特性を活かしながら安定して働き続けるための鍵となります。
カチカでは、障害を持つ方が集中力の波を活かし、強みを発揮するための環境をご提供しています。自分のペースで短時間から始められる作業や特性を最大限に活かせるクリエイティブな仕事を通じて、「自分に合った持続可能な働き方」 を見つけるお手伝いをいたします。
特性と上手く付き合っていくための具体的な一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。