在宅就労を考えている障がいのある方にとって、まず大切なのは「自分を知ること」です。この記事では、自己理解の方法から、障害特性や生活環境に合った在宅就労の選び方、そして仕事を長く続けるための工夫までをわかりやすく解説します。この記事を最後まで読むことで、在宅就労が「なんとなく聞いたことがある」状態から「自分に合った形で安心して働ける」具体的なイメージへと明確になります。
Contents
在宅就労で働きたい障害者の方へ ― 自分に合った求人を見つけるヒント
「自分のペースで働きたい」「外に出るのは難しいけれど収入を得たい」という思いから在宅の求人を探す方は多いでしょう。ただ、仕事内容や環境が合わないまま働き始めると、負担が大きくなり長続きしないこともあります。
だからこそ大切なのが「自己理解」です。自分の特性や体調に合った働き方を知っていれば、求人の選び方や面接での伝え方がスムーズになり、安心して働ける職場に出会いやすくなります。
この章では、そのためのヒントを紹介します。
なぜ、在宅求人を探す前に「自己理解」が大切なのか

物価の上昇などにより、多くの人が生活に不安を感じています。障がいのある方も例外ではありません。「安定した仕事に就かなければ」と焦る方や、「本当は働きたくないけれど、親から家計が厳しいと言われて仕事を勧められる」という方もいるでしょう。
もちろん、働かなければ生活は成り立ちません。しかし実際に働き始めると、想像以上に多くの業務を任されて負担が大きくなったり、上司から厳しい叱責を受けて精神的に傷ついたりするケースも少なくありません。障がいの特性と職場環境が合わず、離職につながることも多いのが現状です。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が令和6年に実施した調査によれば、入社1年後の離職率は次のとおりです。
- 発達障害:71.5%
- 知的障害:68.0%
- 身体障害:60.8%
- 精神障害:49.3%
主な離職理由としては「職場の雰囲気や人間関係」「賃金・労働条件への不満」「仕事内容が合わない」などが多く挙げられています。さらに「症状の悪化」や「障がいのため働けなくなった」という理由も2割を超えています。
一方で、会社側に求められる改善点としては、
- 体調不良時に休みやすい環境づくり
- コミュニケーション支援やサポート人員の配置
- 能力を発揮できる仕事内容の設定
- 短時間勤務など働き方の柔軟さ
などが示されています。
入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチは、単に企業側の問題だけではありません。求職者自身が、自分について深く知ることから、その多くを防ぐことができます。
大切なのは、入社前の段階で、自らの特性や体調に合った働き方・環境はどのようなものかを具体的に整理しておくことです。こうした準備が、長く安心して働き続けられる職場を選ぶための揺るぎない土台となります。つまり、そのような「自己理解」こそが企業と求職者のミスマッチを未然に防ぎ、理想のキャリアを築くための最も重要な第一歩となります。だからこそ、在宅求人を探す前に「自己理解」が欠かせないのです。
自己理解を深めるための方法
では、実際に「自己理解」を深めるにはどうすればよいのでしょうか。
私たちの脳は、目や耳など外の情報を処理する力がとても強い一方で、自分の内側の感覚、気持ちや体調、心の動きを処理する力は意外と弱いと言われています。そのため、自分のことを客観的に見るのは簡単ではありません。
さらに、脳には「認知バイアス」や「防衛反応」と呼ばれる働きもあります。たとえば、友人や知人から「あなたは仕事ができるね」と言われても、「いや、これぐらい普通だよ」と思ってしまったり、逆に「すぐ落ち込むよね」と言われても「そんなことないよ」と否定してしまったりすることは、あなたにも経験があるのではないでしょうか。
とはいえ、だからといって自分をまったく理解できないわけではありません。自分の行動や他人の見方という「事実」と、それに対する自分の感情を少しずつ切り分けてみたり、1つの出来事を細かく分けて観察したりすることで、完全ではなくても「自己理解の仮説」を立てることはできます。
ここからは、自己理解を深めるために具体的にできることを紹介します。少しずつ試してみてください。
①自分の「強み」と「弱み」を書き出す
得意なことや苦手なことを客観的に把握し、自分に合った仕事内容や職場環境を見つけるための第一歩です。
②生活習慣表で働きやすい時間帯を知る
一日の体調や気分の波を記録することで、無理なく安定して働ける時間帯やペースを具体的に知ることができます。
③就労パスポートを活用する
自身の障がい特性や必要な配慮を企業に分かりやすく伝えるためのツールで、面接時などに活用できます。
④分析が難しい場合は障害者職業相談室へ相談
自分一人で自己分析を進めるのが難しい場合でも、専門の相談員が客観的な視点で強みや適職探しを手伝ってくれます。
■関連記事
障害者にとっての在宅勤務の可能性
障害のある方にとって、在宅勤務は「働きやすさ」を大きく変えてくれる選択肢です。通勤がなくなることで体力や精神的な負担が減り、周囲の目や集団の人間関係に悩まされることも少なくなります。その一方で、パソコンやインターネットを通じて会社の一員として業務を担い、社会に貢献することができます。近年は、障害者雇用における在宅勤務の導入も進み、業務内容もライティング・データ入力・オンラインサポートなど幅広くなってきました。家から働ける環境が整ってきた今こそ、在宅勤務は「働きたいけれど不安がある」という方にとって大きな可能性を秘めています。
通勤の負担がないメリット

在宅勤務の最大の特徴は「通勤がいらないこと」です。これは単に移動時間を省けるだけでなく、障害のある方にとって生活や体調の安定に直結する大きなメリットです。
①体力・精神面の負担軽減
厚生労働省の令和5年の障害者雇用実態調査では、多くの障害者が週30時間前後働いており、長時間勤務が体力的・精神的に課題となっています。特に通勤を加えると、一日の消耗がさらに増してしまいます。在宅勤務なら移動の負担がなく、自宅という安心できる環境で働けるため、心身の安定につながります。
(参照:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001233721.pdf)
②交通トラブルのストレス回避
気候変動による大雨や地震、人身事故など、近年は交通トラブルが頻発しています。電車やバスの運行が乱れると、ルート変更や長時間の待機が必要になり、特に精神・発達障害のある方や車椅子利用者にとっては大きなストレスになります。在宅勤務ならこうした不安に振り回されず、落ち着いて仕事に取り組めます。
③混雑回避による安心感
通勤ラッシュの人混みや騒音は、精神的な疲労や不安を強める原因になります。特に人混みや雑音が苦手な方にとっては、出勤前からエネルギーを消耗してしまうことも少なくありません。在宅勤務であれば、そうしたプレッシャーがなく、自分のペースで安心して一日を始めることができます。このように「通勤がない」というだけでも、在宅勤務には生活の質を高める大きな意味があります。
■関連記事
自分のペースで働ける柔軟性
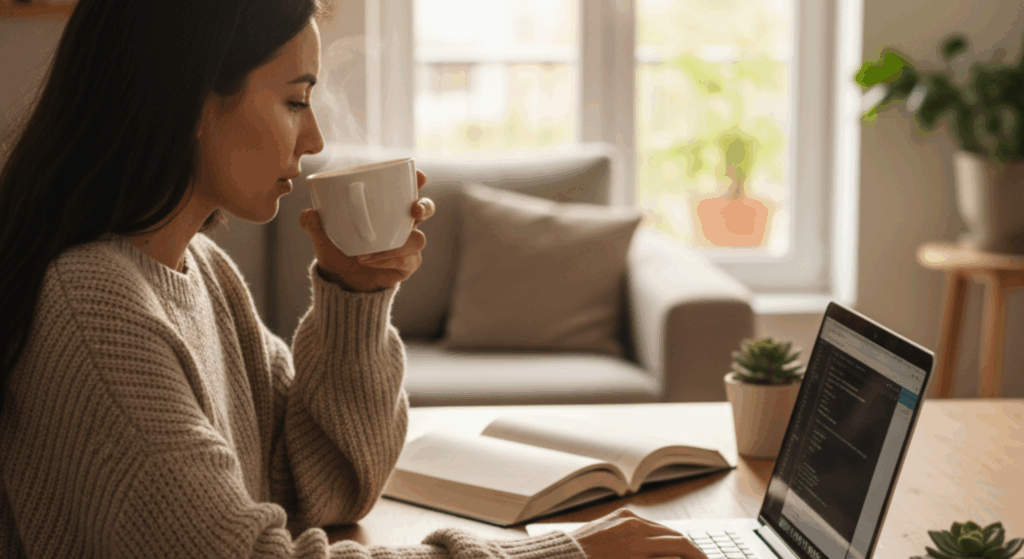
在宅勤務の大きな魅力のひとつは「自分のペースで働ける柔軟性」です。障害のある方にとって、体調や生活リズムに合わせて仕事の仕方を調整できることは、働き続けるうえで非常に重要です。勤務時間や休憩の取り方を自分に合ったスタイルにできることで、無理なく長く働き続ける可能性が広がります。
①体調や集中できる時間帯に合わせて調整可能
人によって「頭がさえる時間帯」や「体が動きやすい時間帯」は異なります。朝が得意な人もいれば、午後から調子が出る人もいます。従来のフルタイム勤務は朝出勤・夕方退勤が基本でしたが、在宅勤務では昼や夜など、自分のリズムに合わせて業務に取り組むことができます。自己理解によって自分に最適な時間帯を見極めることができれば、より効率的に働けます。
②突発的な体調不良や休憩を取りやすい
在宅就労を希望する方の障害の種類によっては、突然の疲労感、痛み、緊張感に襲われることがあります。職場に通っていると周囲の目が気になり、すぐに休むことが難しい場合も少なくありません。しかし在宅勤務であれば、事前に雇用主と体調について共有しておくことで、必要なときに柔軟に休憩が取れます。休息後に体調が戻れば再び仕事を続けられるため、無理せず働き続けることができます。
③家事や療養との両立がしやすい
一人暮らしで家事を担う方や、家族と暮らしていて家庭の役割を担っている方にとっても、在宅勤務は大きな助けになります。また、今は体調が万全ではなくても、在宅勤務なら療養と仕事を両立しながら少しずつ社会とのつながりを持つことが可能です。将来的に通勤勤務を目指す方にとっても、段階的に働く力をつけていく場として在宅勤務は有効です。
仕事の選択肢が広がる

通勤勤務では、暮らしている地域によって応募できる求人に限りがありました。地方や交通の便が悪い地域では、どうしても職種の選択肢が少なくなりがちです。しかし在宅勤務であれば、インターネットとパソコンさえあれば全国どこからでも応募でき、地域に左右されずに幅広い仕事を探すことができます。近年は企業側もオンラインでの採用や研修を整えており、障害者にとって働き方の可能性は大きく広がっています。
①全国どこからでも応募可能
在宅勤務の求人は、居住地を問わずエントリーできるものが多くあります。求人サイト「Indeed」などで「障害者雇用 在宅勤務」と検索すれば、幅広い求人が見つかります。応募の流れもオンライン化が進んでおり、面接や説明会は「Zoom」や「Google Meet」などのWEB会議システムで実施されます。そのため移動の負担なく、自宅から応募から採用まで完結できるのです。
➁多様な職種から選べる
在宅勤務で可能な仕事は年々多様化しています。ライティングやデータ入力、カスタマーサポートといった基礎的な業務に加え、デザイン・プログラミング・動画編集・翻訳など、スキルを活かした専門的な職種にも挑戦できます。自分の得意分野や適性を自己理解したうえで選ぶことで、長く続けられる仕事に出会いやすくなります。
③オンラインツールの進化で安心して働ける
「Chatwork」や「Slack」などのチャットツール、タスク管理アプリ、クラウドストレージの活用により、在宅勤務でもチームとの連携がスムーズになっています。まるでオフィスにいるかのように上司や同僚とコミュニケーションを取りながら業務を進められるため、孤立感を感じにくく、困ったときにはすぐに相談できます。こうした仕組みがあることで、在宅でも安心して働き続けられる環境が整ってきています。
このように、在宅勤務は「場所に縛られない自由」と「幅広い職種の選択肢」、そして「効率的に働ける仕組み」が揃っているため、障害者にとって新しい可能性を広げる働き方といえるでしょう。
在宅就労が向く人・向かない人
ここまで在宅就労のメリットを紹介してきましたが、すべての人に向いているわけではありません。大切なのは「自己理解」を通して、自分の特性や体調、生活環境に合った働き方を選ぶことです。在宅就労は通勤の負担を減らし、自分のペースで働ける柔軟性を持つ一方で、孤立感や自己管理の難しさなどのデメリットもあります。人との関わりが少ないことで逆に不安を感じる人もいれば、在宅より通勤・通所勤務の方が安心できる人もいます。「在宅勤務なら安心」と思って飛び込んでも、実際には続けにくい場合もあるため、自分に合うかどうかを冷静に見極めることが必要です。
「在宅だから安心」とは限らない理由

在宅就労は、自分の部屋で落ち着いて働けるという点で魅力があります。しかし同時に、仕事の開始・終了、報告の仕方、わからないことの質問方法、集中できる環境づくりまで、すべて自分で管理しなければなりません。特にこれまで通勤勤務の経験がない方や、自己判断・パソコン操作に不安がある方にとっては、思わぬ壁になることもあります。
①孤立感やコミュニケーション不足のリスク
在宅就労は一人で作業する時間が多いため、孤立感を覚える人もいます。チャットツールで同僚たちがオフィスで楽しそうに働いている様子を見ると、「自分だけ疎外されているのでは」と不安になることもあります。また、文字だけのやり取りでは意図が伝わりにくく、質問しても「意味がわからない」と返される場合や、専門用語や操作を説明されても理解が難しい場合があります。特に図や実演で理解しやすい人にとっては、チャット中心のやり取りは大きな負担になりやすいです。テキストだけでなく定期的なビデオ通話でのミーティングで認識を合わせるなど、能動的にコミュニケーションの機会を作ることが大切です。
②自宅環境が仕事に向かない場合もある
在宅勤務は周囲の環境に左右されます。狭い部屋で家族と同居している場合や、繁華街の騒音が多い場所では、ADHDや聴覚過敏の人にとって集中が難しくなることがあります。また、山間部など通信環境が安定しない地域では、チャットツールのやり取りや大容量ファイルの送受信がスムーズにいかない場合もあります。在宅勤務を始める前に、自宅の通信環境や作業環境を確認することが大切です。
③自己管理が苦手だと続けにくい
在宅就労は自由度が高い反面、自己管理ができないと継続がむずかしい働き方です。テレビやゲームなどの誘惑に気を取られ、始業時間を守れなかったり、夜更かしによって生活リズムを崩したりすることがあります。また、納期に合わせて計画的に仕事を進める力や、疲れる前にこまめに休憩を入れる工夫も必要です。在宅勤務は一人で作業しているように見えても、実際には企業やチームの一員として成果を出す責任があります。そのためには「自己管理力」や「チームで働いている意識」が欠かせません。
■関連記事
障害特性や環境による違い
在宅就労は、自分の障害特性や生活環境によってメリットにもデメリットにもなり得ます。
「家だから安心」と一概に言えるわけではなく、どんな特性や環境に合うのかを事前に見極めることが大切です。
①障害の種類ごとのメリット・注意点
在宅就労に向きやすい点と注意が必要な点を、障害の種類ごとに紹介します。
- 身体障害・内部障害
移動の負担がなく体力を温存できる反面、同じ姿勢を続けることで身体に負担がかかりやすい。昇降式デスクや補助機器の活用が効果的です。 - ASD(自閉スペクトラム症)
静かな環境で集中しやすい一方、チャットのみのやり取りでは意図が伝わりにくいことがあります。チェックリストや定期的なオンライン面談を取り入れると安心です。 - ADHD
自分のペースで作業できる利点がありますが、自宅の誘惑で集中が途切れやすい傾向があります。タイマーを使った時間管理や作業環境の整理が有効です。 - 精神障害(うつ病・不安障害など)
自宅で安心して働ける一方、孤立感が強まりやすいという課題も。定期的な面談や支援サービスとつながることで孤独感を軽減できます。
②住環境やネット環境の重要なポイント
障害特性だけでなく、住環境や通信環境も在宅就労の大切な要素です。
- 作業スペースが十分にあるか
- 家族や同居者の生活音が支障にならないか
- 安定したネット回線でWEB会議や大容量データの送受信ができるか
もし自宅環境が整いにくい場合は、コワーキングスペースの利用や通信機器の見直しも検討できます。
③感覚過敏による向き・不向き
在宅であっても、感覚過敏のある方にとっては 音・光・匂いといった刺激が大きく影響します。これらは仕事の集中力や継続力を左右する要因となりやすいため、事前に工夫をしておくことが大切です。
- 音に敏感な場合
隣の部屋のテレビの音や外から聞こえる車や工事の音、マンションの上階からの足音など、日常生活の小さな音でも強いストレスになることがあります。集中が途切れると作業効率が下がり、体調不良につながることもあります。対策としては、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓の利用、白色雑音アプリで一定の音を流して周囲の雑音を和らげる方法が有効です。
- 光に敏感な場合
パソコン画面の強い光や蛍光灯のちらつき、直射日光が差し込む部屋などが刺激になり、目の疲れや頭痛、集中力低下を招くことがあります。
画面の明るさを調整する、ブルーライトカット眼鏡を使う、自然光を調整できるカーテンやブラインドを設置することで、快適に働ける環境を整えられます。
- 匂いに敏感な場合
同居家族が料理をしているときの匂いや、洗剤・柔軟剤の匂い、外から入ってくるタバコや排気ガスの匂いなどが強い刺激になることがあります。これが気になると仕事に意識が向かず、長時間集中できません。換気をこまめに行う、空気清浄機を活用する、食事や洗濯の時間を調整して匂いが気にならない時間帯に作業するなどの工夫が役立ちます。
④自分の体験を振り返ることが自己理解につながる
在宅就労の向き不向きを見極めるには、過去の体験を振り返ることが役立ちます。
- 集中できた環境はどんな場所だったか
- 作業に支障が出た環境はどんな状況だったか
- 成功体験や失敗体験の原因は何だったか
こうした自己理解をもとに、自分に合った働き方を選ぶことで、在宅就労のメリットを最大限に活かせます。一方で「刺激がないと集中しにくい」という人もおり、あえてカフェや作業スペースを活用するケースもあります。
“自分にとっての働きやすさ”を知ることの重要性
ここまで「在宅就労が必ずしも安心ではない理由」を見てきましたが、これは「在宅が向かない人がいる」という話ではありません。大切なのは在宅か通勤かにこだわるのではなく、自分にとって一番働きやすい方法を見つけることです。生活状況や障害の状態、キャリアの希望や家庭環境などによって、在宅勤務が合う時期もあれば、通勤のほうが合う時期もあります。また、在宅と通勤を組み合わせて働いている人も少なくないので柔軟に考えることが大切です。
①他人の成功例より、自分の状態・希望・環境を優先
SNSや記事、身近で「在宅勤務で活躍している人」を見ると、つい焦ってしまうかもしれません。しかし大事なのは他人のやり方を真似ることではなく、自分に合った働き方を選ぶことです。たとえば次のような点を振り返ってみましょう。
- 今の自分の障害特性や体調はどうか
- 自分のスキルや、これから伸ばしたい分野は何か
- 始業・終業のリズムをどこまで自己管理できるか
- わからないことを自力で調べたり、質問できる環境はあるか
こうした条件が整っているかどうかで、在宅就労のしやすさは大きく変わります。
②周囲のサポートを活用し、働き方を模索
「自分に合う働き方がよく分からない」という場合は、支援機関を頼るのも有効です。
- ハローワークの障害者窓口や障害者職業センターでは、専門相談員が状況を整理し、向いている働き方を一緒に考えてくれます。
- 体調や健康面に不安がある場合は、主治医に相談することも大切です。必要に応じて訪問看護などの支援につながることもあります。
- 暮らしている地域や障害の種類によって受けられるサービスは異なるため、まずは利用できるサポートを調べてみましょう。
在宅・通勤どちらであっても、「支援を受けながら自分に合った環境を整えること」が、長く安心して働くための第一歩になります。
障害特性に合った在宅就労の選び方
ここまで「在宅就労は誰にでも向いているわけではない」ことを見てきました。では実際に、自分に合った仕事を選ぶにはどうすればよいのでしょうか。第4章では、障害特性や環境に応じて無理なく取り組める在宅就労の選び方を整理します。業務内容やサポート体制の有無などをチェックしながら、あなたに合った働き方を探していきましょう。
業務内容で選ぶ
在宅就労を考えるとき、まず大切なのは「仕事内容が自分の特性に合っているか」です。例えば、コツコツとした作業が得意な方にはデータ入力や事務作業が向きやすい一方、文章を書くのが好きな方はライティングに挑戦しやすいでしょう。逆に、集中力が続きにくい方が長時間のプログラミング案件に取り組むと負担が大きくなってしまいます。求人情報を見るだけでなく、実際に体験や模擬課題に取り組むことで「自分が続けやすいか」を確認することが重要です。
①代表的な在宅職種の例
- 事務・データ入力:ルールが明確、繰り返し作業が得意な人に向く
- ライティング:言語能力・集中力を活かせるが、納期管理が必要
- デザイン・イラスト:感覚や創造性を活かせるが、納期と修正対応も発生
- IT・プログラミング:専門スキルが活きるが、自己解決力や学習継続力が必要
②特性ごとの適性の例
- ASD → ルールやマニュアルが明確な業務(データ入力、コーディングなど)
- ADHD → 短時間で区切れる作業(記事執筆、カスタマーサポートなど)
- 身体障害 → 体力負担の少ないPC業務(ライティング、リモート事務など)
- 精神障害 → 負担の少ない時間・量でできる仕事(在宅事務の一部業務など)
「障害特性=仕事の制限」ではない ここで挙げたのはあくまで一例であり、「ASDだからこの仕事しかできない」「身体障害があるからこの仕事は無理」と決めつけるものではありません。環境を整えたり、スキルを少しずつ伸ばしたりすることで、自分の希望する業務に挑戦できる場合も多くあります。障害特性だけで選ぶのではなく、希望・工夫・成長の余地を含めて総合的に考えることが大切です。
■関連記事
在宅就労の希望条件の整理と伝え方
障害者が在宅求人で働く際に大切なのは、自分の希望条件を整理して、わかりやすく雇用先に伝えることです。希望条件を明確に伝えることは、企業側にとっても採用した人材に長く活躍してもらうための重要なステップです。採用後のミスマッチを防ぎ、安心して働き続ける土台を作れます。
①働ける時間帯・環境・必要な配慮を紙にまとめる
まずは、自分の体調や障害特性、家庭の状況をふまえて、働ける時間帯や必要な配慮を整理しましょう。
- 朝は体調が安定しにくいので午後勤務が希望
- 光に弱いため、照明や画面設定の調整が必要
- 静かな環境であれば集中しやすい
こうした内容を紙やPCにまとめておくと、雇用先に伝えやすくなるだけでなく、自己理解の整理にもつながります。
②仕事の進め方や休み方、評価方法の希望も記載
求人応募や面接で伝える条件は「勤務時間」だけではありません。希望の背景に理由を添えると、雇用先も理解しやすくなります。
- 仕事の進め方:「チャットだけだと仕事の進め方の理解が不十分になることがあるため、必要に応じてビデオ通話で説明を受けたい」
- 休み方:「長時間作業を続けると集中力が途切れるので、1時間ごとに5分休憩を入れると効率が上がる」
- 緊急対応:「体調不良や睡眠障害が出ることがあり、その際は業務を早めに切り上げて別日に調整できると継続しやすい」
- 評価方法:「成果だけでなく、プロセスや努力も見てもらえるとモチベーションを維持できる」
このように「希望+理由」をセットで伝えることで、雇用先も配慮の必要性を理解しやすくなり、採用後の働きやすさにつながります。
③家族や支援者と面接練習をしておく
在宅就労の面接は、ZoomやGoogle Meetなどのオンライン形式で行われることが多いです。対面の面接に比べて表情や声のトーンが伝わりにくく、慣れていないと緊張して言いたいことが出てこない場合もあります。そのため、面接の事前練習は必須です。家族や支援者、就労支援事業所の職員、あるいはハローワークの障害者窓口の担当者に協力してもらい、模擬面接を繰り返しておきましょう。
- 質問に答える練習:「働ける時間帯」「どんな配慮が必要か」といった基本的な質問は、スムーズに答えられるようにしておくと安心です。
- 希望条件を伝える練習:事前にまとめた「働ける時間」「休憩の取り方」「コミュニケーション方法」などを、面接の流れに沿ってどう伝えるかを練習します。
- オンライン環境のチェック:カメラの角度、背景、マイクの音量、ネット回線の安定性も確認しておきましょう。これも面接官に好印象を与えるポイントです。
- 予想外の質問への対応:練習の中であえて答えにくい質問をしてもらうと、本番で焦らず落ち着いて答えられるようになります。
このように「答え方」+「伝え方」+「環境準備」を意識した練習を重ねることで、自信を持って面接に臨むことができます。
■関連記事
在宅勤務の障害者雇用と求人の現状を徹底解説
在宅就労を長続きさせるコツ
在宅就労は始めやすい反面、継続していく中で生活リズムの乱れや孤独感、集中力の低下などに直面しやすい働き方でもあります。ですが、日常の小さな工夫を積み重ねることで安定して働き続けることが可能です。この章では「今日から取り入れられる具体的な工夫」をご紹介します。
生活リズムを安定させる
在宅で働くうえで大切なのは、毎日をできるだけ安定したリズムで過ごすことです。ただし「すぐに生活リズムを整えられる人」と「過眠や昼夜逆転でむずかしい人」では、工夫の仕方が異なります。ここでは両方のケースをふまえて、今日から試せるポイントをまとめます。
①起床・就寝時間をそろえる
・比較的リズムを整えやすい人・・・毎日同じ時間に起きて寝ることが効果的です。体内時計が安定し、仕事中の集中力が高まります。
・昼夜逆転や過眠傾向がある人・・・「午前中に起きる」「作業を始める時間を一定にする」といった、自分に守りやすい基準を設定するのがおすすめです。
➁朝のルーティンを決める
・比較的リズムを整えやすい人・・・顔を洗う、カーテンを開けて光を浴びる、カレンダーを確認するなど、「仕事スイッチ」を入れる習慣を取り入れましょう。
・昼夜逆転や過眠傾向がある人・・・朝一番からフル稼働するのは難しいこともあります。その場合は「起きたらまず水を飲む」「好きな音楽を1曲流す」といった小さなルーティンから始めてもOKです。
③適度な運動を取り入れる
・比較的リズムを整えやすい人・・・日中に散歩やストレッチを取り入れると、夜の睡眠の質が上がりやすくなります。軽く体を動かすことで、頭の切り替えや気分転換にもつながります。
・昼夜逆転や過眠傾向がある人・・・午後に強い眠気が来やすい人は、その時間にあわせて「短時間の昼寝」や「軽作業を配置する」など工夫することで、無理なく働き続けられます。
生活リズムを整えることは「休みなく働き続ける」ことを意味するのではありません。自分に無理のないペースを見つけ、安定して働けるリズムを少しずつ形にして、仕事自体へのモチベーションを高めていくことです。
チャットツールでやり取りを円滑に
在宅では顔を合わせて雑談することが少ないため、ちょっとしたことでも「伝わっているかな」と不安になりやすいものです。その不安を減らすために、チャットツールを活用した 報連相(報告・連絡・相談) が欠かせません。
- 短く・具体的に伝える
「終わりました」「確認お願いします」といった一言でも十分です。長文よりも簡潔にまとめることで、相手に伝わりやすくなります。
- 疑問は早めに聞く
「後でまとめて質問しよう」とため込むと、迷いが増えてストレスにつながります。小さな疑問でも早めに確認する方が効率的です。
- テンプレートや図を活用
業務の流れを図解したり、定型文を用意しておいたりすると、毎回ゼロから考える必要がなくなり、やり取りがスムーズになります。
- チャットとビデオ通話の併用
文字だけで理解しにくいときは、短いビデオ通話をお願いすると誤解が減り、安心感も得られます。
コミュニケーションの工夫を積み重ねることで、「孤独に仕事している」という感覚が減り、モチベーションの維持にもつながります。
集中力の波を活かす
在宅就労では「ずっと集中し続ける」のは難しく、集中できる時間とそうでない時間の波があります。この波を理解し、うまく活かすことが長く働き続けるコツになります。
ただし、ASDやADHDの方の中には「軽くストレッチをしても頭が切り替わらない」「小さく区切るのがかえってストレスになる」という人も少なくありません。そんなときは、無理に一般的な方法を取り入れる必要はありません。
◎ 自然に切り替えられる工夫
- 環境を変える:照明の色を変える、画面をライトモード⇔ダークモードに切り替える
- 媒体を変える:キーボード入力から手書きや音声入力に変える
- 好きなものを挟む:飲み物をひと口飲む、推しの写真を数秒眺める、短い音楽を流す
こうした「小さな刺激」が集中のリズムを作りやすくします。
◎ 切り替えが苦手な場合
- 無理に休憩や切り替えをするのではなく、集中が切れるまで一気に進める
- 苦手な作業に得意な要素(色付け・整理など)を混ぜる
- 単純作業と考える作業を交互に行い、頭を完全に切り替えなくても負荷を変えながら進める
といった「切り替えない工夫」も有効です。
大切なのは「一般的な方法に合わせる」ことではなく、自分の特性に合ったリズムを見つけることです。集中の波を味方につけることで、無理なく在宅就労を続けやすくなります。
体験談から学ぶ
在宅就労を長く続けるためには、実際に働いている人の工夫や姿勢を参考にすることが非常に役立ちます。ここでは、コロナの流行時に在宅就労を経験したカチカのくらげさん(現在は通所勤務)の体験談を通して、在宅勤務での集中力の保ち方や作業の工夫、モチベーションを維持するポイントを紹介します。
◆くらげさん在宅就労記事
①自宅でも作業に集中できる環境
くらげさんはリモートでショート動画制作や事務作業を行っていました。周囲に人がいなくても、音楽をかけるなど自分に合った環境を工夫することで、集中して作業を進められたそうです。
②柔軟な作業時間・リズム
作業開始や終了の時間は自分で調整可能。体調や生活リズムに合わせて無理なく働けるため、在宅勤務でも長く続けることができました。
③サポートを受けながら進める
困ったときは、連絡手段を通じてアドバイスや確認を受けながら作業していました。質問や相談がしやすい環境があることで、安心して仕事に取り組めます。
④成長や達成感が得られる
書類作成や記事作成など、在宅での仕事でも成果が評価される機会があります。新しいスキルを身につけたり、成果を認めてもらったりすることで、自己肯定感やモチベーションが高まったそうです。
くらげさんの経験からわかるように、在宅就労では「自分に合った環境作り」「柔軟な作業時間」「サポートの活用」「成果を感じる工夫」が長く続けるためのポイントです。自宅でも無理なく働きながらスキルを伸ばし、安心して仕事を続けられる環境を整えることが大切です。
まとめ

在宅就労は、障がいのある方にとって働きやすさを大きく広げてくれる選択肢です。ただし「どんな働き方が自分に合うのか」を理解することが、長く安心して働き続けるための第一歩になります。焦らず、自分の特性や生活リズムを少しずつ知りながら、在宅就労の可能性を前向きに広げていきましょう。あなたに合った働き方は、きっと見つかるでしょう。




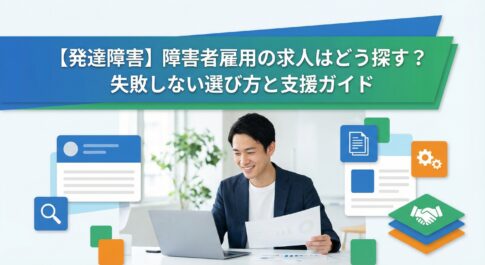







コメントを残す